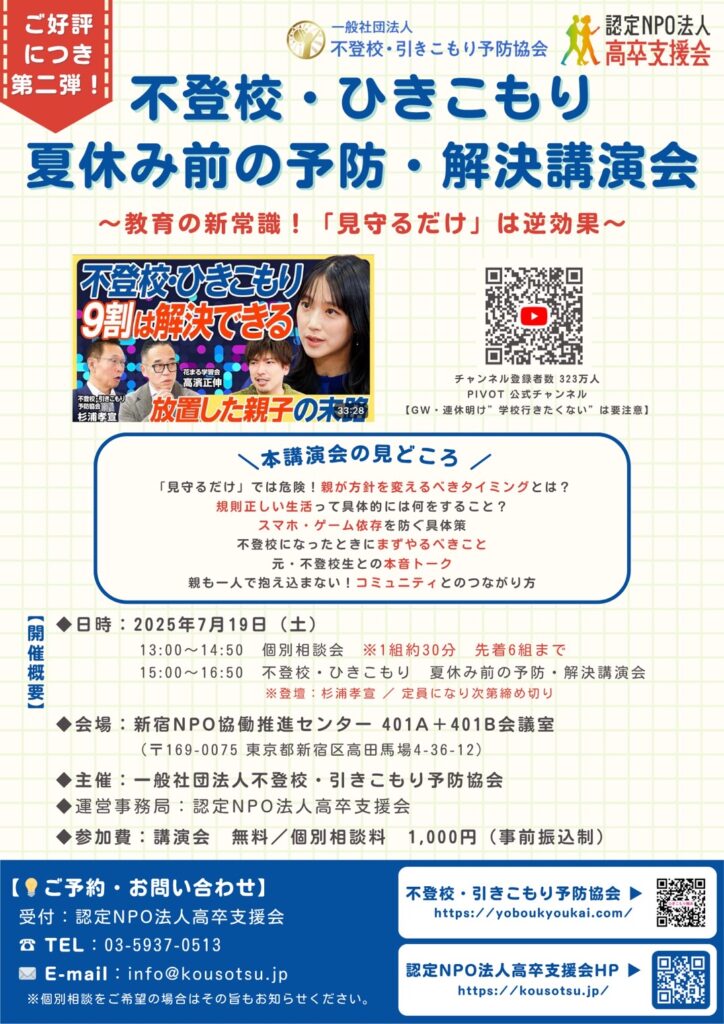40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの
9割を立ち直らせた解決力
まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの
9割を立ち直らせた解決力
まずは30分無料相談へ
こんにちは、一般社団法人不登校引きこもり予防協会の杉浦孝宣です。
私は40年以上、不登校や高校中退・引きこもりの子どもたちを支援してきました。支援人数は1万人以上、9割以上が社会復帰を果たしています。
その中で、ここ10年ほどの「異変」を見逃せません。
不登校になったお子さんが、精神科や心療内科に通院し、すぐに“精神疾患”と診断され、薬を飲むようになってしまう。そんなケースが確実に増えています。
私自身、支援現場で「薬を飲んでから目がうつろになった」「暴力的になった」「まったく笑わなくなった」といったご家族の声を何度も聞いてきました。
もちろん、すべての医療が悪いわけではありません。けれど、「本当にその薬、必要ですか?」と問いかけたいのです。
子どもの不登校や引きこもりを“病気”と決めつけてしまうことの怖さ。
そして、その誤解が、未来ある命を奪ってしまう可能性があること。
この記事では、薬に頼る前にできること、そして薬を使わずに立ち直った子どもたちの実例を通して、
親御さんに知ってほしい支援の形をお伝えします。
不登校になると、まず病院に行く──。そんな流れが、ここ10年で急激に広がっています。私は40年以上、不登校や引きこもりの支援に関わってきましたが、「不登校=精神疾患」と捉えられ、早期から薬を出されるケースが増えている現状には、深い危機感を抱いています。
先日、東京大学で開催された「精神薬の薬害を考えるシンポジウム」に参加しました。講演者の一人は、息子さんを向精神薬の副作用で亡くされたお母さまでした。その方の証言は、親として胸を打たれるものでした。精神科に行けば安心、薬を飲めば改善する──そう信じていたからこそ、取り返しのつかない結果になってしまったのです。
この記事では、「不登校の子どもたちが本当に“精神疾患”なのか?」「薬に頼る前にできることは何か?」という問いを軸に、私の支援現場での経験、そして成功事例を交えながら、保護者の皆様と一緒に考えていきます。
文部科学省の令和5年度統計によると、不登校の中学生は21万6,112人に達し、過去最多を更新しました。年々増加しています。そしてその裏では、「発達障害の傾向がある」「適応障害かもしれない」といった精神医学的な診断を受けるケースが急増しているのです。
特に中学生・高校生においては、「朝起きられない」「無気力」「登校しぶり」などの症状を“うつ”や“発達障害”、あるいは“起立性調節障害”と結びつけられやすく、心療内科を勧められた保護者からの相談も少なくありません。
医療機関での診察は10分程度。「眠れますか?」「食欲は?」といった簡単な問診のあと、すぐに薬が出される。このようなケースを、私は何度も見てきました。保護者は「病院に行ったから安心」「薬を飲めば良くなる」と思いがちですが、実はここに大きな落とし穴があります。
向精神薬(抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など)には、副作用が存在します。よくあるものとしては、頭痛、吐き気、興奮、不安、幻覚、依存症状など。特に発達途中の10代には、思わぬ反応が起きることも。
私の支援団体に来たある男子生徒は、薬を服用後に「感情がなくなった」「目がうつろになった」「暴力的になった」と親が訴えてきました。精神科を受診し、薬をもらい、服用を続けるうちにどんどん悪化。最終的に薬をやめて、生活リズム改善と対話中心の支援に切り替えたことで、彼は回復しました。
シンポジウムで語られたお母さまの実話──。息子さんは大学院生で、先輩との関係に悩み通院を始めました。薬を処方され、調子が悪くなると「薬を増やしましょう」と繰り返され、最終的には命を落としました。母親は「もっと早く、薬の危険性に気づいていれば」と涙ながらに語っていました。
診察時間の短さ、制度上の制限、薬の処方が前提の医療体制。精神科医が悪いのではなく、医療制度そのものが「とりあえず薬を出す」構造になっていることも背景にあります。
子どもが学校に行かない、引きこもっている。そんなとき、親が医療に頼りたくなる気持ちは当然です。「診断がつけば安心」「薬で元気になるかも」──そう思っても不思議ではありません。
ですが、子どもの本当の不登校の理由は、環境、対人関係、自己肯定感の低下など、薬では解決できない問題が多いのです。
私たちは以下の7つのステップで、薬に頼らずに子どもたちを支援しています。
子どもが不登校になるのは、弱いからでも、病気だからでもありません。
たとえば、いじめ、先生とのトラブル、家庭内の問題、過剰な期待──。こうしたストレスに「自分を守るため」に学校から距離を置くのは、人として自然な反応です。
それをすぐに「精神疾患だ」と決めつけてしまえば、子どもは「自分は壊れているんだ」と思い込んでしまいます。
まず、薬を使う前にできることがあります。子どもと会話できていないなら、無理に話さず“安心できる時間”を積み重ねることから。生活リズムが崩れているなら、まず親自身が生活を整えましょう。
私たちの支援機関では、「家庭内の関わり方」→「家庭訪問」→「生活改善」の順で支援を行い、多くの子どもが薬なしで回復しています。
子どもたちは変わる力を持っています。薬や診断に頼る前に、「環境」「関係」「生活」を見直すこと。それが、本当の意味での“再スタート”につながるのです。
もし今、薬を飲ませるべきか迷っているなら、どうか一度立ち止まって相談してください。あなたのその選択が、お子さんの未来を大きく左右するかもしれません。