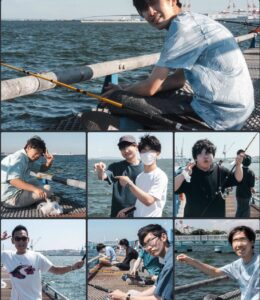40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの
9割を立ち直らせた解決力
まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの
9割を立ち直らせた解決力
まずは30分無料相談へ
中高生の不登校・引きこもりに悩む保護者の皆さまへ
「うちの子、このままで大丈夫だろうか…」
「学校に行かなくなって、もう何ヶ月も経つ」
「話しかけても、返事がない。どうしたらいいのか分からない」
ひどい状況では 親と話さない、昼夜逆転、お風呂も入らない ..
そんな不安を抱えながら、日々を過ごしている保護者の方へ。
はじめまして、一般社団法人不登校・引きこもり予防協会 代表理事の杉浦孝宣です。
このブログは、 中高生の不登校や引きこもりから抜け出すための 具体的な道筋” をお伝えするために書きました。
私たちが40年以上の支援活動を通じて確信していることがあります。
それは、正しい関わり方と支援のタイミングがあれば、子どもは必ず動き出せるということです。
YouTube番組「pivot」でもお話しした「3ステップ支援法」は、これまで1万人以上の子どもたちを支えてきた実践的な方法です。
もし、今「何から始めればいいか分からない」と感じているなら、
このブログが、ご家庭にとっての 第一歩”になるはずです。
ゴールデンウィーク明け、「学校に行きたくない」と言い出す子どもが急増します。
それまで普通に登校していた中学生が突然、布団から出られない、朝になると体調不良を訴える。
そんな場面に直面した保護者からのご相談が、当会にも多く寄せられます。
「まさか、うちの子が不登校になるなんて」 「少し様子を見れば、そのうち元に戻るだろう」
そう考えて 見守る”選択をされた方がほとんどです。
しかし、その ”見守り” が、子どもを長期の引きこもりへと進ませてしまう危険性があることをご存じでしょうか?
私たちはこれまで40年以上にわたり、不登校・引きこもり支援に携わってきました。
その経験から断言できるのは、「早期の正しい関わりこそが、子どもの未来を守るカギ」だということです。
今回、YouTube番組「pivot」にて花まる学習会代表・高濱正伸先生と共に、支援の現場で培った 3ステップ支援 についてお話ししました。
このブログでは、その出演内容をもとに、中学生の不登校・引きこもりに悩むご家庭が、どのように対応すればよいかを丁寧に解説していきます。
「今、何をすればいいのか分からない」――そんな不安を抱えるすべての保護者の方に、少しでも希望の道筋を届けたいと思います。
中学受験を頑張り抜き、晴れて中高一貫の私立校に進学したわが子——
順調に見えていたのに、ゴールデンウィーク明けに突然「学校に行きたくない」と言い出す…。
そんなご相談が、今まさに急増しています。
私・杉浦孝宣が出演した教育系YouTube番組「#pivot」では、
「中高一貫校進学後に不登校になった」というリアルな事例が多く寄せられ、大きな反響を呼びました。
▼【前編】不登校・引きこもりは9割解決できる!
スマホ・ゲーム依存対策/「見守り=放置」の落とし穴/重症度チェック付き
▶️ https://youtu.be/UjT1xHGcLO0?si=b8wo9Bu4CiqgQqh4
▼【後編】年齢別の対応法と立ち直りの3ステップ
同性の親の関わり方/学力の壁への向き合い方
▶️ https://youtu.be/qLQnFUBvG6M?si=ggFwi3Tky0QFcjWI
番組では、花まる学習会・高濱正伸先生とともに、
『もう悩まない!不登校・ひきこもりの9割は解決できる』をベースに、
親の具体的な関わり方、そして子どもの立ち直りのプロセスについて詳しく解説しています。
私たちははっきりと断言します。
“見守る”だけでは、子どもの未来は変わりません。親の行動こそが、未来を変える鍵なのです。
ぜひご視聴の上、ご家庭での対応のヒントにしていただければと思います。
「不登校は見守りましょう」――
これは、今や多くの教育現場やネット上で当たり前のように語られる言葉です。確かに、無理やり学校へ行かせることが逆効果になるケースはあります。子ども本人の意思を尊重し、安心できる環境を整えることは非常に重要です。
しかし、「見守る」ことが「何もしない」ことにすり替わってしまっているケースが、私たちの支援現場では非常に多く見られます。
ある保護者はこう言いました。
「先生、 ”見守る”って言われたから何もしないようにしていました。半年たっても状況は変わらず、今では昼夜逆転し、部屋から一歩も出てきません」
こうした事例は少なくありません。
中学生という時期は、思春期による心身の変化、進路への不安、友人関係の悩みなど、さまざまなストレスが一気に重なる時期です。
そこに 無関心に見える”見守り”が加わると、子どもは「親にも頼れない」「誰にも気持ちを理解されない」と感じ、内へ内へと閉じこもってしまいます。
さらにスマホやゲームの存在も、引きこもりを助長する要因になります。 「ゲームの世界のほうが楽」「誰にも怒られないから安心」となれば、ますます外に出る意欲は失われていきます。
つまり、 ”見守る”とは本来、「子どもの変化を感じ取り、必要なときに適切に関わること」でなければなりません。
具体的には
といった「関わりを伴う見守り」が必要です。
私たちがpivotで紹介した 3ステップ支援”は、まさにこの「見守るだけでは変わらない」状況を打開するための実践的な方法です。
不登校や引きこもりの問題に直面する家族は、その状況を理解し、対処するために、子どもの状態を「ステージ」として捉えることが有効で、pivotで解説しました
この分類に基づき、各ステージに応じた具体的なサポートの提供方法をご紹介します
家族の皆さんが一丸となって、この課題に取り組むことの重要性を強調します。ちなみに カイト君はステージ判定3でした。
ステージ1 不登校の初期段階
不登校期間 1日~60日
対応 親子間のコミュニケーションを重視し、子どもの話をじっくりと聞きます。
生活リズムの乱れが見られない限り、まずは家庭内での安定を図ります。食事は3食しっかりと取るようにし、規則正しい生活習慣を支援します。
ステージ2 不登校が続く場合
不登校期間 61日~180日
対応 親子間のコミュニケーションは保ちつつ、生活リズムの乱れに注意を払います。
この段階で学校や専門家との相談を始めることをお勧めします。
食事に関しても、バランスの取れたものを心掛けましょう。
ステージ3 長期不登校から引きこもりに
不登校期間 181日~
対応 この段階では、第三者の介入が必要になる場合が多いです。
生活リズムの乱れを正し、食事の管理も含めて外部の専門家の助けを借りることが有効です。
ステージ4 引きこもりが顕著に
特徴 自室に閉じこもりがちで、親子間のコミュニケーションが極めて困難に。
対応 専門のカウンセリングやカウンセラーの支援を積極的に求めます。
家族内での対応だけでなく、外部の支援を活用して、子どもが社会に復帰できるようなプランを立てます。
ステージ5 長期化した引きこもり
特徴 20歳を超えて引きこもりが続いており、社会復帰が困難。
対応 この段階での支援はより専門的なものが求められます。社会復帰支援プログラムや、成人向けの支援施設の活用を検討します。
家族もサポートを受けることが重要です。
不登校や引きこもりを経験する子ども達とその家族にとって、一人で抱え込む必要はありません。
各ステージに応じた適切な支援と、家族や周囲の理解があれば、困難な状況を乗り越えることが可能です。
大切なのは、子どもと向き合い、一歩ずつ前に進むことです。
| 不登校期間 | 親子間のコミュニケーション | 生活リズム | 食事 | |
| ステージ 1 | 1日~60日 | △ | △ | 〇 |
| ステージ 2 | 61日~180日 | △ | × | △ |
| ステージ 3 | 181日~ | × | × | △ |
| ステージ 4 | 年単位 | × | × | × |
| ステージ 5 | 年齢20歳以上 | × | × | × |
「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学,非常勤職を含む就労,家庭外 での交遊など)を回避し,
原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状 態(他者と交わらない形)
私たちがYouTube番組「pivot」で紹介したのが、「3ステップ支援」と呼ばれる方法です。これは40年以上にわたる現場支援から導き出された、実践的かつ再現性の高いアプローチです。
この3ステップは、不登校から引きこもりに進行してしまうのを防ぎ、子どもたちが自分の力で社会に再び踏み出していけるようサポートするための流れです。
最初のステップは「生活リズムの改善」です。
不登校の子どもの多くは、昼夜逆転し、朝起きられず、食事も不規則になりがちです。
そのままの状態で勉強や登校、外出といった ハードルの高いこと”を求めても、本人にとっては到底無理な話です。まずは、以下のようなシンプルな目標から始めます。
このステップの主目的は、 体を整えること”です。身体が整えば、心も少しずつ前向きになっていきます。
次のステップでは、「親子の信頼関係の再構築」に取り組みます。
不登校や引きこもりが長引くと、親と子の間に 言葉ではない壁”ができてしまうことが多いのです。特に中学生は、思春期によって親の言葉に反発したり、恥ずかしさから素直になれなかったりするもの。
ここで大切なのは、叱るのではなく、共感の言葉をかけることです。
さらに効果的なのは、同性の親が関わること。父親が息子に、母親が娘に、対等な立場で接してあげることで、心の距離が一気に縮まることがあります。
生活と関係性が整ってきたら、いよいよ「社会との接点づくり」に進みます。
このステップで重要なのは、「学校に戻すこと」をゴールにしないということ。子どもにとって最も負担の少ない場所から、 ちょっとした外の世界”とつながる機会をつくっていきます。
具体例
子どもが「自分にもできた」「人と話せた」「認められた」と感じられる経験が、 自信の芽”になります。
そしてこの芽を、ゆっくりと確実に育てていくのが、私たち大人の役割です。
Y子さんは中学2年から不登校になり、そのまま中学校を卒業しました。その後、10年間引きこもりの状態が続きました。
親知らずが痛み出したことで外に出るきっかけができ、24歳で私たちの団体に相談に来ました。
私たちはY子さんに学び直すことを勧め、アルバイトを始めることを支援しました。27歳で私たちの通信制高校を卒業し、
短大に進学。保育士の資格を取得し、現在は公務員として活躍。「高校中退 不登校引きこもりでもやり直せる」登場人物
10年間、引きこもったY子さんの経緯と対応を動画に収めました
カイト君は、中高一貫校の中学1年のゴールデンウィーク明けから学校に行かなくなりました。
その結果、自宅に引きこもるようになりました。彼の両親は私たちのアドバイスに従い、一致した教育方針を持つことを試みました。私たちの引きこもり予防士の訪問とサポートにより、
7ヶ月間の支援の後、カイト君は自分から私たちのフリースクールに通うことを選びました中学生の間は毎日フリースクールに通い、高校に進学した後は、私たちと提携している通信制高校に進学しました。
2023年3月に卒業し、現在は自衛隊で働いています 2024年後輩の卒業式にも参加 自衛隊でエンジョイしています
「不登校ひきこもりの9割は治せる」の登場人物
カイト君が保護者会で公務員を目指している事を発表しています
カズキ君は中学受験で中高一貫の私立校に合格しましたが、中学1年から成績不振が続き、高校1年の6月に自主退学を余儀なくされました。
カズキ君は家庭内で暴力や暴言を使うようになりましたが、私たちは彼に適切な居場所を提供することで状況を改善することができました。彼は私たちの通信制高校に転校し、卒業後、都内の区役所で公務員として活躍しています。
「不登校ひきこもりの9割は治せる」の登場人物
公務員として活躍中のカズキ君が保護者会で立ち直った様子を講演してくれました
リョウタ君は昨年の夏休み明けから学校を休みがちになり、10月には完全に不登校になりました。
家では一切話さず、毎日自室に閉じこもり、携帯ゲームばかりしていました。
親が作った食事を拒否し、カップラーメンだけで過ごしました。彼の親は学校に相談しましたが、状況は一向に改善せず、
リョウタ君の母親は何をすれば良いのかわからず、私たちに相談しました。
家庭訪問(アウトリーチ支援)を開始し、その後彼は私たちの通信制高校に転校しました。
2023年9月には航空自衛隊への入隊
「不登校ひきこもり急増」の登場人物
中学受験で私立の中高一貫校に入学した中1の5月から不登校に陥りました。母親は有名な不登校専門家に相談し、
「不登校は放っておけばよい」と言われたため、何の対策もせずに中学を不登校のまま卒業しました。
その後、不登校児を受け入れる全寮制高校に進学しましたが、高1の冬休みにバリケードを作って引きこもりました。
当会の支援で父親が本気を出して向き合ったことで引きこもりから脱し、創業したフリースクールに通うようになり、通信制高校を卒業しました。
一浪して有名難関大学を卒業し、現在は公務員として活躍中
公務員として活躍中のタツマ W君が保護者会で立ち直った様子を講演してくれました
スポーツ推薦で私立高校に進学しましたが、練習場まで家から1時間30分以上かかるところにあり、野球部の練習は早朝から夜まで続くハードな練習で、挫折してしまいました。
部活に出られないと高校にもいられない雰囲気となり、当会に都立高校への相談に来ました。本人は都立校に転学を希望していたため、当会で支援をすることになりました。
しかし、その後は当会にも来ず、1年4ヶ月 引きこもってしまいました。
継続的な支援をした結果、やっと自力で外に出ることができるようになり、当会の提携する通信制高校に通い、入学当初は友達を作らなくていい思っていましたが、
様々なイベントに参加体験をすることでクラスメートと仲良くなり、自信をつけて卒業しました。現在は北海道の大学で農業を勉強しています
朝日新聞の「耕論」に、「ゲーム1時間」条例について佐藤渉太さんが記事が掲載されました
ショータ君のコミュニケーションを鍛えるため、Youtube ダラダラトークもしました
2025年 JA内定を受けて、1年4ヶ月の引きこもりから どのように立ち直ったか 佐藤君が語ってくれました
高1のシュン君は、6月末から学校を休み、昼夜逆転の生活でゲームばかりしています。学校に行かなくなった原因は友達とのトラブルだと話しています。
完全な引きこもりであることが特徴として挙げられます。親と話さない、昼夜逆転、ゲーム漬け、外出が少なく、お風呂に入らないなどが含まれます。
アウトリーチ訪問支援を行いました。シュン君は部屋で寝ていました。話し始めると、朝から晩までiPadでゲームをしているとのことで、学校の友達とゲームの時間を合わせて4か月過ごしていました。
勉強を始める時期だと感じているようですが、復学の意思はないと話しています。
スタッフの勧めで当会の通信制高校に転校しましたが、生活習慣の乱れを治すために生活改善合宿や学生寮などを実施しました。
一定の効果はありましたが、高校卒業を迎え、「働きたくないから予備校に行かせてくれ」と発言しました。
私も呆れ、スタッフに「自衛隊または住み込みでどこかに働かせて、本当に大学に行きたいなら、自分でお金を貯めて」とアドバイスしました。
ご両親も納得して、箱根のホテルに住み込みで働きに行きました。その年の12月、お母さんから「あれからシュンも頑張って働いたので、予備校通いを認め、看護系の大学に受かった」と連絡がありました
シュン君と一緒に海釣りに行った時の様子を動画にあげました
W君は通信制高校のネットコースに在籍しており、昼夜逆転や引きこもりが加速したため、8ヶ月間引きこもっていました。
このような学校に通うことで、自宅で勉強できるため人気がありますが、一部の生徒にとっては引きこもりを加速させてしまう可能性があることが、彼の例から明らかになりました。
私と面談した彼は、自身の生い立ちや全日制高校でうまくいかなかった理由、そして通信制高校に入った後の経験について素直に話しました。
それにより、彼は自分自身の状況をより深く理解し、解決策を探すための第一歩を踏み出しました。
その後、彼は私が創業した通信制高校サポート校に入学し、学生寮に入って毎日学校に通える環境を提供されました。
その結果、彼は早稲田大学進学を目指すなど、自身の将来に向けた積極的な姿勢を取り戻しました。
防衛大学の一次試験には合格しましたが、面接試験では残念ながら落ちてしまいました。
それでも高校を卒業し、現在は自衛隊で活躍しています。
W君自身が8ヶ月間引きこもった理由と原因について語った動画インタビューや
不登校保護者会で発表されたPTAだより 必見!
エイタ君は、中学受験で私立の中高一貫校に進学しましたが、中1の3学期から徐々に不登校に陥り、中2の4月から完全な不登校となりました。
中2の11月には引きこもりステージ判定3の状態に陥りました。ご両親が私の講演会に参加し、訪問アウトリーチ支援を受け始めました。
中3の6月にはインターンのカイト君を信頼するようになり、家から出ることができるようになりました。その後、フリースクールを創業し、生徒会会長に就任し、動画編集会社を運営するまで元気になりました。
しかし、責任が重くなり、フリースクールに来なくなり、引きこもりに再び陥りました。スタッフの訪問によって再び立ち直り、高3に進級し、2023年6月に1ヶ月間のカナダ留学を経験しました。
7月には成果報告を保護者会で発表しました 不登校保護者会で本人発表 pta 動画含む だより エイタ君の親御さんが書いたPTAだより
2024年3月高校卒業。工学院大学建築学部入学と同時に学生インターン開始
不登校が悪化し、8ヶ月間引きこもっていた高校生のG君が美大に合格しました。中学までは問題なく登校していた彼ですが、受験を機にネガティブになり、
入学3日で不登校し、留年確定となり退学してしまいました。G君は長時間ゲームをしており、外出もせず、家族との会話も気分次第でした。
特に弟に対して優しくなかったこともあり、彼も不安定になっていました。
このような状況が約8ヶ月間続き、G君のおばあさんが私の著作を読んで、ご両親に紹介してくれました。それがきっかけで、私たちスタッフと出会いました。
G君は家業の手伝いをするようになり、保護者からの依頼で家庭訪問を受けました。スタッフと相談した結果、高校卒業資格を取るため、
創業したフリースクールに通うことになりました。G君はフリースクールで同じ境遇の子たちと打ち解け、方向性が決まりました。
翌年の4月までは、中学時代の学び直しと月2回以上のイベントに参加しました。
その年の4月、G君は一年遅れで通信制高校に1年生として入学しました。G君はまだ進路を決めていませんでしたが
不登校や引きこもりから脱け出すため、毎日コースに入学しました。彼のイラストが評価され、パンフレットやHPの画像を制作することになりました。
しかし、eスポーツに熱中して生活が乱れたため、フリースクールを辞め、オンラインコースに切り替え、通学回数を減らし、美大の塾と自宅で勉強しました。
美大合格に向けて、彼は集中しました。1以前はサポート校に通学していたため、通学しないで、人との会話がなくなることが心配でしたが、
スタッフに相談し、本人のペースで通学しつつ、美大向けの塾に通い、見事合格を果たしました。
2023年4月以降、フリースクールで学生インターンで後輩に美術を教えています。
中学時代の不登校、高校でのいじめを経て、海外留学を試みるも失敗。しかし、帰国後、フリースクールで学び直し、自信を取り戻し、新たな自立への道を歩み始めます。
彼は、学生寮での生活改善、学業への再挑戦を通じて、自らを変え、青山学院大学へ進学。大学でのプレゼンテーション能力向上やコンペ参加を経て、大手IT企業への就職に成功
中高一貫校 での不登校,昼夜逆転を経験し、
その後,当会、通信制高校サポート校 へ転校して プライム上場企業に内定を勝ち取ったサコウ君。
相談に来た時は学校生活に適応することが困難で、多くの時間をゲームで過ごしていましたが生活習慣 を改善し、
新たな学びの場所である通信制高校で自信と意欲を取り戻しました
中学生の頃に不登校、引きこもりとなり、6ヶ月間、入院。
発達障害の診断を受けて入院生活を送ったW君。
進路が見えず、ご家族も悩みを抱えていた状況から、当会の通信制高校サポート校
に入学。適切な支援と本人の努力で新たな道を切り開き、現在は看護系の大学に進学し、医療機関への就職を目指しています!
中学3年で不登校宣言、その後、2年間、引きこもる。7ヶ月間、当会支援し解決! 通信制高校への進学を決断し、現在は週5日通学中。
カナダ留学も経験しました。将来、農業従事者を目指しています
2025年4月 農業系の大学に進学しました!
【2年間引きこもった子の保護者出演】
不登校保護者会で本人発表 PTA動画含む だより
これらの事例は成功例の1部です。不登校や引きこもりの状態からでも、適切な支援によって立ち直り、社会に戻ることが可能であることを示しています。
さらに詳しい事例や詳細な情報は、私の著書「高校中退・不登校引きこもりでもやり直せる」「不登校ひきこもりの9割は治せる」「不登校ひきこもり急増」にて紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください
これらの事例は、不登校や引きこもりが一時的な問題であること、適切なサポートと環境があれば乗り越えられることを示しています。当会では、このような多くの子どもたちの未来を明るく照らすサポートを続けています
「学校に行けなくなったら、まず学校や教育委員会に相談しましょう」と、多くの情報には書かれています。もちろんそれは間違っていません。しかし、実際に支援の現場に立っている私たちから見ると、残念ながら それだけでは足りない”というケースが非常に多いのです。
学校現場の先生方は日々の授業、校務、部活動、保護者対応などで忙殺されており、不登校の生徒にじっくり関わる時間を確保できないのが現実です。また、スクールカウンセラーも月に数回の勤務で、継続的な心理的支援を十分に行える体制ではありません。
さらに問題なのが、文部科学省の「不登校は無理に登校させず、見守りましょう」という基本方針。この言葉だけが一人歩きし、 何もしない”ことが保護者の間でも正解のように受け取られてしまっているのです。
一方、自治体が運営する「教育支援センター(適応指導教室)」の利用率は全国平均で10%程度。つまり、約9割の不登校生徒は、学校にも、支援機関にもつながっていないということになります。
支援が届いていない、というより、支援に出会えていないのです。
そして、不登校の状態が長引けば、やがて引きこもりに進行します。実際、内閣府の調査では、若年層(15〜39歳)の引きこもり人口は全国で約61万人、高齢化も進み、40歳以上の引きこもりは推定で100万人を超えています。
これらの現実を前にして、私たちはどうすべきか?
答えは明確です。
家庭での一歩を踏み出すこと、そして、民間で実績を上げている支援機関につながること。
私たちがこれまで行ってきた家庭訪問型アウトリーチ支援では、100件以上の訪問のうち88%が引きこもり状態の改善につながりました。学校でも、行政でも届かなかった支援が、 家庭の中”で行われたことで、子どもたちは再び動き出したのです。
制度が整うのを待つよりも、まずは家庭と地域が連携して子どもを支える体制を築く。それが今、不登校や引きこもりの解決に最も必要なことだと私たちは考えています。
不登校や引きこもりは、誰にでも起こり得る 社会の問題”です。特別な家庭の話ではなく、誰の身近にも存在する課題です。そして、そこに必要なのは「早期の気づき」と「具体的な行動」です。
私たちがYouTube番組「pivot」で伝えたかったのは、まさにその一点です。
子どもは、ほんの小さなきっかけで動き出す力を持っています。 家庭の中での声かけ、生活習慣の整え、そして外部とのつながり。 そのどれもが、再スタートのきっかけになり得ます。
ですが、最も大切なのは「待つだけではなく、働きかける」という姿勢です。
放置でも過干渉でもなく、子どもの状況に応じた 関わり方”を模索すること。
本ブログでご紹介した「3ステップ支援」には、1万人以上の子どもたちを支援してきた現場の知恵と経験が詰まっています。
もしあなたが、 「うちの子に何ができるだろう」 「何から始めればいいのか分からない」 と感じているなら、ぜひこのブログをヒントに、今日からできることを探してみてください。
あなたの一歩が、お子さんの未来を大きく変えるはずです。
一般社団法人 不登校・引きこもり予防協会では、不登校・高校中退・引きこもりに関するご相談を無料で受け付けています。
「誰に相談すればいいのか分からない」
「どこにも頼れる場所がない」
そんなときこそ、お気軽にご相談ください。
あなたとお子さんの未来を、一緒に考えていきましょう。
一般社団法人 未来自律支援機構(JADA)は、前身の「不登校・引きこもり予防協会」より40年以上にわたり、「子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち、自律し、社会に貢献する未来を実現する」という教育ミッションを掲げてきました。
私たちは、不登校や引きこもりを単なる「休養」で終わらせず、社会で生き抜くための「自律(Autonomous Development)」へと導く専門機関です。これまで1万人以上の子供たちをサポートし、社会復帰率9割以上という圧倒的な実績を誇ります。
これらのステップを実践し、1万人以上の子どもたちが変わり、成功率は9割以上を誇ります。
こうした活動はNHK「おはよう日本」 プレジデントオンライン Youtube pivotでは前編+後編 45万超再生回数 多くの親御さんに希望を届けました。
加えて成功事例が満載のリンク集を参考にしていただきたいと思います。当会のミッションに共感し、真剣にお子さんの不登校や引きこもりを解決したい方、ぜひ私たちと一緒に取り組みましょう。一緒にお子さんの未来を輝ける人生に切り開いていきましょう!時間は待ってくれません。不安を感じたその時が、解決への第一歩を踏み出すチャンスです。私たちと一緒にお子さんの未来を守りましょう!