
40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの
9割を立ち直らせた解決力
まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの
9割を立ち直らせた解決力
まずは30分無料相談へ
「中学受験、やめた方がいいのかな……」
「でも、本人は“やっぱり受けたい”って言ってる……」
学校に通えなくなった小学6年生が、中学受験のことで揺れ動いているとき、保護者の気持ちもまた大きく揺れます。
・学校には週1回しか行けない
・行事には参加できるけど、通常の授業は難しい
・受験は辞めてもいいと言ったのに、また「受けたい」と言い始めた
・家庭ではゲームに没頭し、夫婦間での対応もズレがある……
――こうした複雑な状況に、どう対応すればいいのか分からず、悩んでいませんか?
一般社団法人不登校引きこもり予防協会の代表理事 杉浦孝宣です
このブログでは、体育の授業での心の傷がきっかけで不登校になった小学生の事例をもとに、「中学受験」と「不登校」が交差する時期に、保護者として何ができるのかを具体的に解説します。
さらに、当協会が実践してきた7つの支援ステップや、安心して学び直せるフリースクールの活用法、そして【成功事例】や【今後の支援イベント(講演会・合宿)】の情報もご紹介。
「うちの子にも、まだ可能性はあるのかも――」
そう思えるヒントが、きっと見つかるはずです。
まずは、親が“焦らず・諦めず・一歩を踏み出すこと”から始めてみませんか?
「中学受験はやめてもいい。でも、ここまで頑張ったから、やっぱり受けたい」
これは、ある小学校6年生の男の子が口にした言葉です。
4月以降、学校にほとんど通えなくなってしまった彼は、週に一度、水曜日だけ登校しています。友達関係に問題はなく、生活リズムも整っています。でも、どうしても「毎日の登校」は難しい。先生から言われた一言が心に残り、その記憶がよみがえってしまうからです。
そんな状況でも、本人は中学受験を「やめたくない」と言います。
ただ、以前のように塾に通うのは難しくなり、今は本人の希望で、個別指導の塾に切り替えて学びを続けています。
このご家庭のように、「不登校気味の状態でも受験をしたいという意欲がある」小学生は、実は少なくありません。
保護者としては、
と、日々、迷いと葛藤の中にいらっしゃることでしょう。
実際、私たちのところにも、同じような悩みを抱えたご相談が数多く寄せられています。
ここで大切にしたいのは、「受験する・しない」の二択で子どもを判断しないことです。
子どもにとっては、
「行けない学校があること」と
「行きたい学校があること」は、まったく別の感情です。
たとえば、今の学校に行けないのは、過去の体育の授業での一言がきっかけだったり、集団での活動が苦手だったりと、理由があります。
それでも、「新しい環境でなら頑張りたい」と思える子もいます。
このような“希望の芽”が見えたとき、私たち大人がするべきことは「結果を急がず、環境を整えること」です。
心が折れたまま、無理に受験を続けさせてはいけません。
でも、せっかく子どもが「もう一度挑戦したい」と言っているなら、その想いを大切に育てる方法もあります。
それが、フリースクールなどの「安心できる学びの場」を活用するという選択肢です。
学校には行けないけれど、家だけでは学びにくい。そんな子にとって、フリースクールは心の安全基地になります。
「学校に行かない=勉強しない」「受験をあきらめる=失敗」ではありません。
子ども自身の気持ちとペースに合わせて、「心の土台」を整えていくことで、不登校状態でも受験にチャレンジする道は開けていきます。
このブログでは、実際の成功事例も紹介しながら、「中学受験」と「不登校」が交差する小6の揺れる心に寄り添い、どのような支援や選択肢があるのかを詳しく解説していきます。
どうか一人で抱え込まず、前向きな一歩を踏み出すきっかけにしていただけたらと思います。
「せっかく頑張ってたのに、先生から“君は全くできないね”って言われた。もう、やりたくなかった。」
これは、小学6年生の男の子が口にした、体育の授業での一言によって学校が嫌になったきっかけです。
運動が苦手な子どもにとって、体育の時間は毎週訪れる「試練」のような時間です。
その中でも、組体操やリレーの練習などで「みんなと同じ動きをしなきゃいけない」「ミスが目立ちやすい」場面では、先生の何気ない一言が子どもの心を深く傷つけてしまうことがあります。
この男の子も、5年生の3月に行われた卒業生向けの組体操練習で、仲間と一緒に真剣に取り組んでいました。けれども、体育の先生からの厳しい言葉で、努力が否定されたように感じ、「頑張ってもムダなんだ」と思ってしまったのです。
その日から、学校=否定される場所、体育=怖い時間、という感情が、彼の中に根付いてしまいました。
◆ 不登校のきっかけは「小さな心の傷」から
不登校というと、いじめや家庭問題など大きな要因を想像する方も多いでしょう。
けれども、実際に多くのご相談を受けていると、「たった一言」がきっかけで学校に行けなくなる子がたくさんいます。
子どもたちの心は、とても繊細でまっすぐです。
特に、責任感が強くて真面目なタイプの子ほど、少しの否定や誤解がトラウマになりやすいのです。
このように、不登校の原因は「目に見える問題」ではなく、「心の奥に残る痛み」であることが多いのです。
◆ 本人も理由をうまく説明できないことがある
保護者の方が「なぜ行けないの?」と聞いても、子どもがうまく説明できないことがあります。
それは、心の中で言葉にならない「違和感」や「怖さ」を抱えているからです。
この男の子も、当初は「わからないけど、行きたくない」としか言えませんでした。
しかし、ゆっくりと時間をかけて関係性が築かれたとき、「体育の先生のことを思い出すと怖くなる」とポツリと語ってくれたのです。
大人からすれば「たったそれだけで?」と思ってしまうような出来事でも、子どもにとっては人生を変えるような出来事なのです。
◆ 学校の“すべて”が嫌なわけではない
興味深いのは、この男の子が移動教室などのイベントには喜んで参加しているということです。
決して「学校=全部イヤ」ではないのです。
つまり、彼にとっては「ある特定の時間」「ある特定の先生」と関わるのが辛いだけ。
これは非常に重要なポイントです。
不登校は「すべて拒否している」わけではなく、特定の場面や感情に引っかかりを感じているだけというケースが多いのです。
その“引っかかり”を丁寧に見つけ、解きほぐしていくことが支援の第一歩になります。
「たかが体育」「たかが一言」と軽く考えないでください。
小学生の心には、大人の言葉が一生刻まれることがあるのです。
次章では、このような「特定の場面にだけ参加できる」子どもたちの特徴と、そこから見えてくる不登校の新しいかたちについて詳しく解説します。
「移動教室は楽しかったよ」「〇〇くんと一緒の班で、夜もたくさん話せた」
この言葉を聞いたとき、きっと保護者の方は少しホッとされたことでしょう。
「やっと学校に行けるようになるかも」「これで元通りに戻れるかも」と。
けれども、期待とは裏腹に、翌週からまた通常の登校には戻れない。
行けるのは、週に一度、水曜日の4時間だけ。
これは、いま急増している「イベント参加型の不登校」の典型例です。
◆ 不登校=完全不登校ではない時代
かつての不登校は、「まったく学校に行けない」「家から出られない」というイメージが強かったかもしれません。
けれども今は違います。週1回だけ登校する子、行事には出られるけれど通常授業は無理な子、逆に勉強だけは出席する子……。
子どもたちの不登校は“グラデーション化”しているのです。
この男の子も、「集団の中で体育をすること」や「決められたルールに従うこと」がストレスの原因であり、すべての授業が嫌なわけではありません。むしろ、宿泊行事や自由度の高い活動では、楽しそうに過ごす姿を見せています。
◆ 「行けた日」ばかりに一喜一憂しないで
保護者としては、子どもが久しぶりに学校へ行った日、笑顔で帰ってきた日には、「このまま行けるようになるのでは」と期待してしまうものです。
でも、翌日にまた登校を渋る姿を見て「なんで?昨日は楽しかったじゃない」と落胆してしまう。
この“ジェットコースターのような感情の揺れ”は、保護者の心をすり減らします。
でも、どうか焦らないでください。
不登校の回復には「揺れ戻し」があるのが当たり前なのです。
子どもにとって、行事に参加できたのは「一歩前進」であっても、通常の授業に戻るにはまだ心の準備が整っていないのかもしれません。
回復は一直線ではなく、「2歩進んで1歩戻る」くらいの感覚で見守ることが大切です。
◆ 子どもの“できた”を肯定する
ここで大切なのは、「なぜ行けないの?」と問い詰めるよりも、
「行けたね」「楽しかったんだね」「よかったね」と成功体験を共有することです。
たとえば、こういった声かけが有効です:
このような言葉をかけることで、子どもは「理解してくれている」と感じ、次の一歩を自分から踏み出せる可能性が高まります。
◆ 親が“回復の基準”を間違えないために
「今日も行けなかった」「またサボったのかも」と、日々の登校状況だけを見てしまうと、親の不安やイライラが先行してしまいます。
でも、行事に参加できたこと、週に1回でも登校できていること、
これは、回復のサインなのです。
私たちの支援現場では、「0から1」への変化を非常に大切にしています。
完全に行けなかった子が1時間だけ教室に入れた、週1回だけ顔を出せた――。
それは本人にとっても、家族にとっても、未来への確かな一歩なのです。
不登校とは、「行けない状態」ではなく、「行ける力を取り戻すまでの時間」と捉え直してみてください。
次章では、そんな“回復の途中”で重要な要素となる、ゲームとの付き合い方と家庭内の方針のズレについてお話ししていきます。
「ゲームばかりして、勉強も学校もどうでもよくなってるんじゃないか…」
「中学受験をするなら、そろそろゲーム時間を減らしていかないと…」
不登校の状態で家にいる時間が長くなると、どうしても保護者としてはゲームの存在が気になってきます。
実際、今回の小6の男の子も、平日の学校には行けていないものの、自宅では毎日数時間、ゲームに没頭しています。
父親は「心の支えになっているなら仕方ない」とある程度認める姿勢を見せていますが、母親は「このままでは勉強もできなくなる」と不安を募らせており、家庭内でも意見が食い違ってきています。
◆ ゲーム=悪ではない。だけど“扱い方”が重要
私たちの現場でも、ゲームに依存するように見える子どもたちは少なくありません。
けれども、その背景を丁寧に聞いていくと、実はゲームが「孤独から救ってくれたもの」「心を保つ手段」になっているケースが多くあります。
例えば——
そんな時、ゲームの世界は「安心できる場所」だったのです。
失敗しても怒られない。自分のペースで動ける。自分が活躍できる場面もある。
つまり、ゲームに夢中になる子どもは、「逃げている」のではなく「守っている」のです、自分の心を。
◆ 親が“奪う存在”になってはいけない
ここでやってはいけないのが、「もうゲームは禁止!」「こんなことしてる暇ないでしょ!」という強引な取り上げです。
たとえ正論であっても、それは子どもにとって“唯一の居場所”を壊す行為に映ります。
「また親に否定された」「どうせ分かってもらえない」
そう思わせてしまえば、子どもはますます心を閉ざし、時には暴言や反抗につながることも。
重要なのは、ゲームを否定せず、適切な距離感を一緒に考えることです。
◆ 徐々に“外の世界”を取り戻す
この男の子のように、ゲームが心の支えになっていた子でも、フリースクールや家庭訪問、ピアサポートなど、信頼できる人との関わりができてくると、ゲーム以外の世界にも目を向けられるようになります。
このように、「減らす」ではなく「広げる」発想で取り組むことが大切です。
◆ 父と母で意見が違うときは?
家庭の中で、ゲームに対するスタンスが違うこともよくあります。
このご家庭のように、父は寛容、母は否定的というケースでは、子どもが混乱したり、どちらの顔色をうかがうようになったりしてしまうことも。
そのため、保護者同士で共通のルールをすり合わせておくことが非常に重要です。
たとえば——
このようなルールを“親が一方的に押しつける”のではなく、“子どもと一緒に決める”ことで、本人も納得感を持ちやすくなります。
ゲームを敵にせず、味方につける。
それが、今の子どもたちを理解し、支えていく上で欠かせない視点です。
次章では、そうした「心の安全」を確保しながら、もう一度受験に挑戦しようとする子どもの意欲と、どう向き合っていけばいいのかをお伝えします。
「中学受験、やっぱりやめようかな……」
学校にも通えず、塾も辞め、毎日不安な表情を浮かべていたある日。
その男の子は、ぽつりとこう言いました。
——「でも…やっぱり、ここまで頑張ってきたから、受けてみたい気持ちもあるんだ」
この一言は、親にとってとても複雑なものでした。
「やめてもいい」と伝えたはずなのに、「やりたい」と言う。
それが本心なのか、それとも“親をがっかりさせたくない”という無意識の罪悪感なのか。
慎重に見極めなければならない場面です。
◆ かつての受験は“親の希望”だったかもしれない
もともと、この子が中学受験を始めたきっかけは、決して本人の強い希望ではありませんでした。
「みんな受けるから」「このまま地元の中学じゃ不安だから」という周囲の空気の中で、「頑張ろうね」と始まったのです。
親としても、子どもの将来を思ってのこと。
けれど、知らず知らずのうちに“勉強を強いられる日々”になり、負担が積み重なっていきました。
特に塾の集団授業では、周囲との競争やプレッシャーに飲み込まれ、自分を見失っていたかもしれません。
そしてついに、「学校にも行けない」「塾も辞める」状態に。
一度は、受験そのものをあきらめようとしたのです。
◆ “もう一度やりたい”が出たのは、「心が落ち着いた」証拠
そんな中、生活のペースを取り戻し、家庭内の緊張もほぐれてきた頃。
ゲームやお手伝いをしながらも、自分の気持ちに少しずつ向き合えるようになってきた。
そんなある日、
「受験、ちょっと頑張ってみようかな」と自分から言い出したのです。
この「やってみたい」という気持ちは、強制されたものではありません。
心が少し落ち着いたことで、“自分で選ぶ力”が戻ってきたのです。
このような気持ちの変化が見られた時、私たちは支援の中で「いよいよ本格的な再スタートの準備ができてきた」と判断します。
◆ 今度は“親が支える側”に立つ
ここでの親の役割は、“管理者”ではなく、“伴走者”になることです。
代わりに、こう声をかけてみてください:
“見守る”というより、“安心して寄りかかれる存在になる”ことが、再チャレンジを後押しするカギになります。
◆ 「中学受験」はゴールじゃない、“再スタートの通過点”
たとえ不登校状態であっても、本人が「もう一度やってみたい」と言い出せたなら、それは「心の回復」が始まっている証です。
私たちはそれを、学校への復帰よりも大切な「回復のサイン」として捉えます。
ただし、再スタートを切るなら、以前と同じ環境・同じやり方に戻るのはNGです。
個別指導、フリースクールとの併用、家庭訪問など、子どもの気持ちに寄り添った設計が求められます。
受験に挑戦する・しないではなく、「子どもが再び、自分の意思で動き出した」こと自体を大切にしていきましょう。
“やらされる受験”は子どもを疲れさせるけれど、
“やってみたい受験”は、子どもを成長させる。
次章では、そんな揺れる心をしっかり支えてくれる「フリースクールという居場所の役割」について詳しく解説します。
「学校には行けないけれど、フリースクールなら行ける」
これは、決して特別なことではありません。
不登校の子どもたちにとって、フリースクールは「学校でも家庭でもない、心を休められる第三の場所」として、年々その重要性が高まっています。
今回の男の子も、体育の授業をきっかけに「学校=怖い場所」という認識が強くなってしまいました。
けれども、移動教室や個別指導の塾には通えているように、「すべてを拒否しているわけではない」のです。
その「行ける場所」「信頼できる人」があるかどうかで、子どもの“その後”は大きく変わっていきます。
◆ フリースクールは“登校刺激”を与えない
学校に戻してあげたい。
保護者の多くは、子どもの不登校が続くと「やっぱり学校に行かせないと」と焦ってしまいがちです。
けれど、心がまだ回復していない状態で無理に登校を促すと、さらに不安や抵抗が強まり、逆に悪化してしまうケースが後を絶ちません。
その点、フリースクールは「学校に戻すこと」を前提としていません。
まずは“安心して過ごせる場所”を提供し、生活リズムや自己肯定感を少しずつ取り戻すところから始めます。
その中で自然と、「何かを学びたい」「誰かと関わりたい」といった気持ちが生まれてくるのです。
◆ 小学生も安心して通える少人数・個別対応
フリースクールと聞くと、「中高生向け」のイメージを持たれる方もいるかもしれません。
ですが、当協会や連携先のように、小学生から受け入れているフリースクールも増えています。
学校で感じていた「集団のプレッシャー」や「できないことへの恐れ」がない場所だからこそ、子どもはリラックスし、少しずつ「自分らしさ」を取り戻していけるのです。
◆ 子どもが変わり始める“きっかけ”に
支援の現場では、こんな声をよく耳にします。
こうした変化は、決して特別な支援があったからではなく、本人が安心できる“安全基地”を得られたことによるものです。
学校や塾とは違い、評価されることも、怒られることもなく、ただ「受け入れられる場所」がある。
その安心感が、子どもを一歩ずつ前に進ませていくのです。
◆ フリースクール×中学受験の両立も可能
フリースクールは「受験とは無縁」と思われがちですが、実は中学受験と両立している子も増えています。
この男の子のように、個別指導塾で勉強を進めつつ、フリースクールで生活リズムや社会性を整える。
そんな“ハイブリッド型”の取り組みが、今では一般的になりつつあります。
むしろ、学校に通えず不安定な状態で、無理に受験勉強を詰め込むよりも、フリースクールで「安心できる日常」を確保してから挑む方が、長期的に見て成功しやすいというデータもあります。
「学校に行かせなきゃ」と焦る前に、
「安心して過ごせる場所」を確保してあげてください。
子どもが“もう一度頑張ってみようかな”と思えるのは、心が安全なときだけなのです。
次章では、実際にフリースクール×受験で変わった子どもたちの成功事例をご紹介します。
「うちの子に中学受験なんてもう無理かも…」
不登校が続き、家庭での学習も進まない中で、そう感じてしまうのは当然のことです。
けれど、フリースクールを活用することで、中学受験への意欲を取り戻し、合格をつかんだ子どもたちも確かに存在します。
ここでは、そんな子どもたちの「実際の回復と挑戦のストーリー」を紹介します。
◆ 事例①:「もう受験なんて無理」から半年後に私立中へ合格
小学6年の春から突然学校に行けなくなったAくん。
原因は、担任からの厳しい指導と、集団での体育における失敗体験でした。
家にこもりがちになり、母親は焦る日々。中学受験も諦めかけていました。
しかし、フリースクールに週3回通うようになったことで状況が変化します。
最初はゲームの話しかできなかったAくんが、スタッフとの信頼関係を築くうちに、「また勉強してみようかな」と口にするようになったのです。
その後、個別指導塾と併用しながら無理のないペースで受験勉強を再開。
志望校も自分で決め、「面接では自分のことを話せた!」と笑顔を見せるまでに回復しました。
結果、第一志望の私立中学に合格。現在も元気に通学を続けています。
◆ 事例②:受験をやめたけれど、自信を取り戻して公立中で元気に
Bさんは小学5年から不登校。中学受験のために塾に通っていましたが、周囲のプレッシャーで精神的に疲れ果て、家に引きこもるようになりました。
そんな中、母親が見つけたのがフリースクール。
「学校じゃないけど、行ってもいい場所がある」と思えることで、徐々に外に出られるようになりました。
最終的にBさんは中学受験は辞退しましたが、その選択を“逃げ”とは思っていません。
「自分の気持ちで決められたことが嬉しかった」
「これからは自分のペースでやっていきたい」
中学入学後も不登校は再発せず、現在は友達との関係も良好に過ごしています。
◆ 事例③:「学校には行かないけど、受験はしたい!」を叶えた男の子
Cくんは、学校の先生との関係が原因で完全不登校に。
けれども、「今の学校は無理だけど、受験して別の中学に行きたい」という強い思いを持っていました。
そこで家庭では「勉強を頑張るなら学校に行かなくてもいい」と割り切り、フリースクール+個別塾のスタイルを選択。
勉強も生活もフリースクール内で整え、受験日には自分の足で会場へ向かいました。
志望校には惜しくも届きませんでしたが、その努力と経験がCくんの大きな自信となり、現在は別の中学で充実した日々を送っています。
◆ 合格よりも大切なのは「自分で決めた」という経験
これらの子どもたちに共通していたのは、「フリースクールで安心できる居場所があったこと」、
そして、「受験する・しないを自分で選んだこと」です。
中学受験は、親にとっては大きなイベントかもしれませんが、子どもにとっては「人生最初の自己決定の場」です。
その選択を、焦りや不安から大人が奪ってしまうのではなく、フリースクールという環境の中で心を回復させながら、“自分で選ぶ力”を取り戻す。
それが、本当の意味での「進路選び」であり、「子どもの成長」なのです。
不登校でも、挑戦できる。
挑戦しなくても、自分で決められる。
フリースクールは、そんな選択肢をすべて包み込む“余白”のある場所です。
次章では、そうした柔軟な環境づくりを支えるために、保護者ができるサポートの具体例をお伝えします。
「この子にとって、今いちばん必要なことは何だろう?」
不登校、そして受験という選択肢の間で揺れる子どもを前に、保護者の方は不安や迷いでいっぱいになるはずです。
けれども、親が「今できること」は、意外にもシンプルで力強いものです。
ここでは、私たちの支援現場で実際に効果のあった「3つのサポート」をご紹介します。
① 子どもを“評価”せず、“観察”する
まず最も大切なのは、「良し悪し」で子どもを判断しないことです。
こうした“評価の目”で見てしまうと、子どもはすぐに防御モードに入ってしまいます。
代わりに、子どもを“観察”する目を持ちましょう。
こうした小さな“変化の兆し”に気づき、そっと心の中で拍手を送ってあげてください。
「見てくれてる」「受け入れてくれてる」と感じた時、子どもは一歩前に進めるのです。
② 家庭内の方針を“すり合わせる”
次に必要なのが、「両親のスタンスを揃える」ことです。
不登校や中学受験における保護者間のすれ違いは、子どもにとって大きなストレスになります。
たとえば今回のケースでは、
——こうした意見のズレが、結果的に「誰を信じればいいのか分からない」と子どもを混乱させてしまいます。
家庭内で意見が割れることは自然なことです。
だからこそ、大切なのは“夫婦で対話する時間”を持つこと。
・「どんな未来を子どもに望んでいるのか」
・「今は何を優先するべきか」
・「ゲーム・受験・フリースクールへの考え方」
このような点について、一度冷静に話し合ってみてください。
そして、子どもには「お父さんとお母さん、ちゃんと話し合ったよ」と伝えること。
その一言だけで、子どもは驚くほど安心するのです。
③ 第三者と“つながる勇気”を持つ
どんなに努力しても、家庭だけで乗り越えられないこともあります。
そんなときこそ、外部の支援や専門家の力を借りてください。
当協会でもこれまで、こうした多様な支援を組み合わせることで、子どもたちの再スタートを数多く支えてきました。
保護者の方にお伝えしたいのは、「支援を受ける=親としてダメなわけではない」ということ。
むしろ、“ひとりで抱え込まない選択”をした時点で、子育てのステージが次の段階へ進んでいるのです。
子どもが変わるためには、まず親が変わる。
でもそれは、「我慢する」ことでも「完璧になる」ことでもありません。
「見守る姿勢」と「適度な頼り方」を知ること——
それが、保護者にできる最高のサポートなのです。
次章では、実際にそのような支援の流れを体系的にまとめた、当協会の「7つの支援ステップ」と、フリースクールの具体的活用方法について詳しくご紹介します。
「フリースクールに通わせてみようかな……でも、これで本当に変わるのだろうか?」
「このまま家で様子を見ていても、時間だけが過ぎてしまいそう」
不登校のわが子に向き合う中で、そんな迷いや不安を抱える保護者は少なくありません。
私たち一般社団法人不登校引きこもり予防協会では、40年以上にわたる支援実績から、不登校・引きこもり・中学受験のすべてに対応できる“7つの支援ステップ”を体系化しています。
これは「フリースクールに通わせればすべて解決」という考え方ではなく、子どもの状態に応じて“必要な支援を段階的に組み合わせていく”アプローチです。
◆ 支援マップ:7つの支援ステップとは?
🟢 STEP1|ステージ判定(現状把握)
まずはお子さんの状態を冷静に観察し、以下のような段階に分類します:
この“ステージ判定”をもとに、最適な支援の順番と内容を設計していきます。
🟡 STEP2|親のためのコーチング
実は、親の関わり方が変わるだけで、子どもが大きく動き出すケースが非常に多いのです。
不登校支援の第一歩は「子ども」ではなく、「親」の変化から始まります。
🔵 STEP3|家庭訪問支援
「家から出るのが難しい」「スクールに行くのはまだ不安」
そんなお子さんには、学生インターンや支援員による家庭訪問(アウトリーチ)を行います。
最初はドア越しの会話から、徐々に同じ空間でゲームをする、散歩に行くなど、対話と信頼を築いていきます。
🟣 STEP4|生活改善合宿・学生寮
生活リズムの乱れがある場合は、4泊5日の生活改善合宿や、ルールある寮生活の体験を提案します。
スマホやゲームから距離を置き、「自分で起きて、自分で考えて、自分で生活する」という原点に戻る時間です。
※小学生は通所型・デイプログラム対応が中心になります。
🟤 STEP5|学び直し(フリースクール・個別学習)
ここで登場するのがフリースクールです。
小学生でも通える安心・少人数の空間で、勉強の遅れを取り戻すと同時に、生活・人間関係・自信の回復をサポートします。
「中学受験したい」という希望がある子には、塾との併用も可能です。
🔴 STEP6|アルバイト・インターン(中学生以上対象)
年齢が上がれば、社会との接点づくりとしてインターン体験や、学習支援インターン制度も提供しています。
※小学生はこの段階に進むことは少ないですが、将来へのモデルとして保護者にご紹介しています。
🟠 STEP7|社会貢献・自律支援
支援の最終段階では、「ありがとう」と言われる体験や、「誰かの役に立てた」という実感を通して、“自律”と“社会との接点”を育んでいきます。
中学受験後の再不登校を防ぐためにも、この“自律の意識”を早い段階から育てていくことが重要です。
◆ フリースクールをどの段階で取り入れるか?
小学生にとってのフリースクールは、「学校に戻す」ためではなく、「もう一度、“自分”に戻る」ための場です。
こうした心のモヤモヤをリセットし、安心・挑戦・達成のサイクルを少しずつ回し始めるための場所。
「まだ完全不登校ではないけど、毎日学校に行くのはつらい」
そんな状態のときに、週1回からでも通所を始めておくことで、悪化の予防にもなります。
「元に戻す」のではなく、「新しいステージへ進む」ための支援。
それが、当協会の7ステップです。
最終章では、「不登校や受験という言葉に振り回されないために大切なこと」をお伝えします。
「毎日学校に行って、当たり前のように授業を受けて、受験勉強もしてくれたら……」
そんな“普通”ができない状況に、戸惑いや焦りを感じている方も多いかもしれません。
けれど、私たちは支援の現場で確信しています。
「学校に行けるかどうか」よりも、
「子どもが安心して生きていけるかどうか」の方がずっと大切だと。
今回ご紹介した小6の男の子のように、
体育の授業での一言がきっかけで不登校になってしまったとしても、
「もう一度、受験にチャレンジしたい」と自ら言い出せる日が来ることがあります。
その変化の背景には、家庭の理解と、フリースクールという“安全な居場所”の存在がありました。
◆ 不登校は“止まっている”のではない
子どもは、何もしていないように見える時でも、心の中で葛藤し、ゆっくりと前に進む準備をしています。
こうした“ほんの少しの前向きさ”を、親が見逃さずに受け止めてあげること。
それが、子どもの未来を支える力になります。
◆ 大切なのは“合格”より“選べた”という経験
進学先や受験結果よりも、「自分で選ぶ」「自分で動く」という経験こそが、人生を自分の足で歩いていくための第一歩です。
その背中を、私たち大人が信じて支えてあげましょう。
◆ まずは、親が一歩踏み出すことから
「どうしたらいいのかわからない」
「このままでいいのか不安……」
そんなときこそ、私たちにご相談ください。
✅【30分無料個別相談】受付中
✅交通費をご負担いただければ、全国どこでも家庭訪問可能です。
🔹【オンライン講演会のお知らせ】
10月12日(日)13:00〜14:30/Zoom開催(全国対応)
テーマ:「不登校とひきこもりの違い ~それに伴う“対応の違い”とは?」
講師:杉浦孝宣(支援歴40年以上)・大倉星耶(中級ひきこもり予防士)
▶ お申し込み:https://x.gd/iYpfh
※参加費:1,000円(税込)/申込締切:10月11日(土)18:00
🔸【生活改善合宿のご案内】
10月24日(金)〜28日(火)[4泊5日]/東京都八王子市
場所:大学セミナーハウス(緑豊かな自然環境)
対象:生活リズムの乱れやスマホ依存がある不登校・ひきこもり傾向のお子さん
費用:67,400円(税込)
主催:認定NPO法人高卒支援会/共催:一般社団法人不登校引きこもり予防協会
🔗 詳細・お申し込みは、個別相談または当協会HPよりご案内しています。
“子どもは変われる”——その力を、信じてあげてください。
親の小さな一歩が、子どもの人生を動かす第一歩になります。
▶ 【無料相談のお申し込みはこちら】
https://yoboukyoukai.com/soudan/
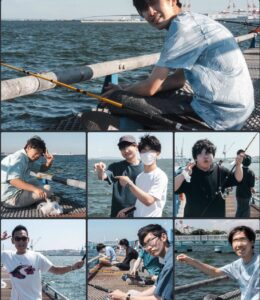



![[WARNING] PATRICIDE & THE MYTH OF WAITING](https://yoboukyoukai.com/wp-content/uploads/2026/02/スクリーンショット-2026-02-01-6.25.13-300x160.png)


