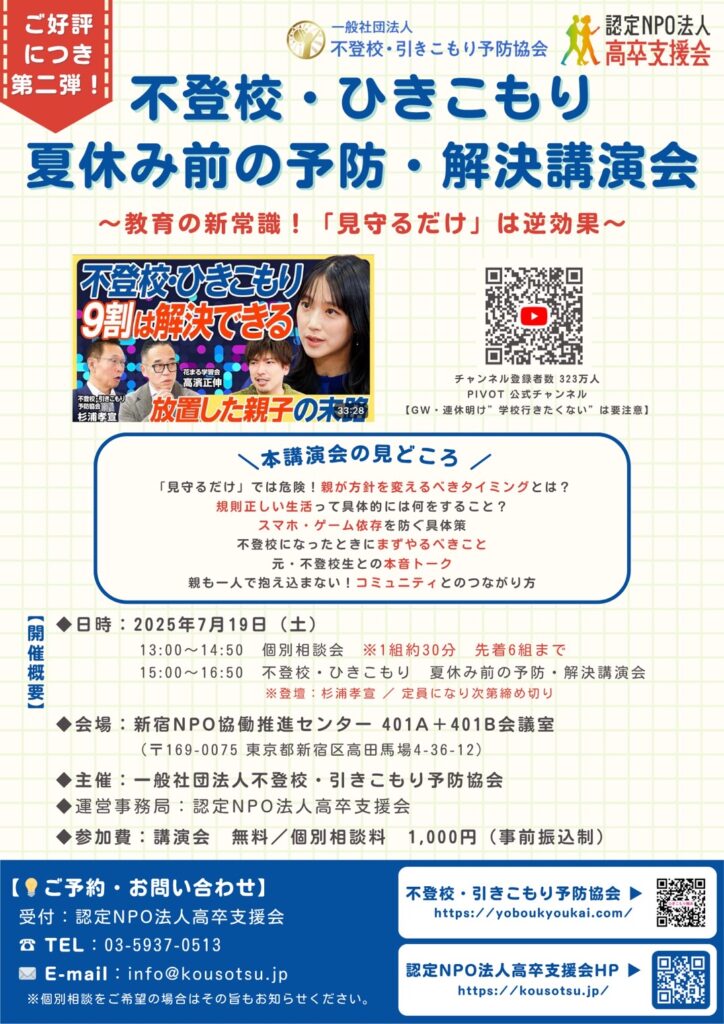40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの
9割を立ち直らせた解決力
まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの
9割を立ち直らせた解決力
まずは30分無料相談へ
はじめまして。一般社団法人不登校引きこもり予防協会の杉浦孝宣です。
私は40年以上にわたり、不登校・高校中退・引きこもりの子どもたちを支援し、1万人以上の再スタートに関わってきました。
そのなかで強く感じるのは――子どもは変われる。けれど、“きっかけ”が必要だということです。
最近では、「どこに相談すればいいかわからない」「支援団体が多すぎて選べない」といった保護者の声を多くいただきます。
また、「もう様子を見すぎたかもしれない」「このままでは引きこもりになるのでは…」という不安を抱えたご家庭も少なくありません。
そこで今回のブログでは、当協会が長年の支援現場で積み上げてきた「7つのステップ支援」について、
そして、成功率9割を支える“伴走型支援”の実際と、16人の実例を交えて、できる限りわかりやすくお伝えします。
さらに、「まず親ができる行動は?」「今の子どもの状態はどの段階なのか?」といった疑問にもお応えしながら、
就職・自律までを見据えた“不登校支援の地図”を一緒に描いていきます。
「うちの子も変われるのだろうか?」
そんな思いをお持ちの方にこそ、読んでいただきたい内容です。
どうか最後までお付き合いください。
そして、次の一歩を私たちと一緒に踏み出していただけたら幸いです。
「このままで本当に大丈夫なんだろうか……」
不登校になったお子さんを前に、ほとんどの保護者の方が、こうした不安を一度は感じています。
最初は「ちょっと疲れてるだけかな」「一時的なものかもしれない」と思っていたのに、気づけば数ヶ月、そして半年、1年…。時間が経つほどに心配は大きくなり、でも、どうすればいいのかは見えないまま。
多くのご家庭が抱える“モヤモヤ”は、主に次のようなものです:
私たち一般社団法人不登校引きこもり予防協会にも、こうした声が毎日のように寄せられています。
特に増えているのは、「すでに1年以上経ってしまった」「本人はほとんど話さないし、部屋から出てこない」という深刻なケース。
「“引きこもり予備軍”の状態だったのに、様子を見ていたら完全な引きこもりになってしまった」
これは、実際に多くの保護者が後悔とともに語る声です。
一方で、支援を求めたくても、「どうせ動かないし…」「何か変化がないと相談しても意味がないのでは?」と、自ら支援への第一歩を踏み出せない方も少なくありません。
支援に関する情報はネット上にあふれていますが、“比較できない支援団体”に迷い、結局は「動かない理由」にしてしまうことも。
だからこそ、私たちはお伝えしたいのです。
「“様子を見るだけ”では、事態は好転しない」ことがあるということを。
もちろん、子どもの回復には時間も、タイミングも必要です。
しかし、今の状況を「見える化」し、具体的なステップを知るだけでも、親としての不安は大きく軽減されるのです。
お子さんのために、今、親としてできることは何か?
その答えを、私たちは「就職まで見据えた伴走型支援」として、多くのご家庭と一緒に探し続けてきました。
結論から申し上げます。
不登校や引きこもりの状態にあるお子さんに対して、「就職まで見据えた長期的な視点での支援」こそが、最も確実で、親として安心できる方法です。
多くの支援は、「まずは学校に戻すこと」「とにかく登校させること」を目標にしがちです。
確かに、学校に戻ることは大切な一歩かもしれません。でも――本当に目指すべきゴールは「登校」ではなく、
「将来自律して社会とつながること」ではないでしょうか。
私たち一般社団法人不登校引きこもり予防協会は、この考えに基づき、就職・進学・自律までを一貫して支援する“伴走型”の支援スタイルを実践しています。
特長は次の3つです:
登校再開だけにこだわると、子どもにとってプレッシャーになります。
一度無理やり登校させても、根本の問題(生活リズム、自己肯定感、家庭環境など)が解決していなければ、再び不登校になってしまうことも少なくありません。
だからこそ、私たちは「登校」よりも「社会に出る準備」を重視します。
「親の関わり方がわからない」「声をかけるのが怖い」と感じている方も大丈夫。
ステップごとに“親の学び直し”を取り入れながら、一緒に支援に取り組めるよう設計されています。
親御さん自身が安心し、自信を取り戻していくことも、お子さんの回復には不可欠です。
支援を受けてきた子どもたちの中には、公務員、自衛隊、大学進学、大手企業への就職など、立派に社会で活躍している例が多数あります。
カイト君(不登校から7ヶ月で支援→自衛隊)、Y子さん(10年の引きこもり→保育士→公務員)など、「長く苦しんでも、やり直せた」実例があるからこそ、私たちも自信を持ってサポートができます。
「今の状態から、ここまで行けるなんて思っていませんでした」
「うちの子が“働きたい”と言い出したのは初めてでした」
これは、実際に支援を受けた保護者の方々から寄せられた言葉です。
何をしても変わらなかった――
そう感じていたご家庭でも、方向性が見えた瞬間から、状況は大きく動き始めます。
迷っている方へ、伝えたいことがあります。
支援には、“一気に治す魔法”はありません。けれど、“確実に前進できる地図”はあるのです。
次章では、その「支援の地図=7つのステップ」について、実例と共に詳しくご紹介します。
お子さんの未来を変えるヒントが、きっと見つかります。
私たちの支援が「不登校・引きこもりの9割を解決できる」と自信を持ってお伝えできるのは、これまで実際に効果をあげてきた“7つのステップ”があるからです。
このステップは、一人ひとりの状況に合わせた“再スタートの道しるべ”。
途中でつまずいても、どこで立ち止まっているかが明確にわかるから、次の一歩も見えてきます。
ここでは、その具体的な内容をご紹介します。
支援の第一歩は、「今、どんな状態なのか?」を正しく理解することです。
たとえば、「不登校」と「引きこもり」では必要な対応がまったく異なります。
同じように見えても、「朝起きられない」「昼夜逆転」「親と口をきかない」などの状態は、ステージ2〜5までのどこにいるかで対策が変わります。
▶ あるご家庭では…
「まだ話せるし、引きこもりではないと思っていた」という保護者の方が、ステージ判定を通して、すでに“引きこもりの入り口”に差しかかっていることに気づかれました。
この現状把握こそが、的確な支援を始める土台になります。
次に行うのは、「子どもに関わる前に、親御さんの心と行動を整える」ことです。
「声のかけ方がわからない」
「逆効果になってしまいそうで怖い」
そう感じている保護者の方がほとんどです。
だからこそ、私たちは月1回のZoomコーチングや、LINEでのやり取りを通して、“正しい関わり方”を一緒に練習していきます。
▶ あるお母さまは…
「つい正論をぶつけていた」「子どもが余計に心を閉ざしていた」と気づき、関わり方を変えたことで、お子さんが初めて「学校に行ってないの、悪いと思ってる」と本音を話してくれたそうです。
どんなに優しい声かけでも、親子だけでは変化を起こすのが難しいことがあります。
だから、信頼できる支援員やインターンが直接ご家庭に訪問し、「無理のない距離感」でお子さんと関わっていきます。
▶ カイト君の例:
中学1年から不登校だったカイト君は、7ヶ月間の家庭訪問を経て、ようやく支援員とゲームの話をし、そこから心を開き始めました。最終的には自衛隊に入隊し、今も元気に働いています。
「学校に行かないと何もできない」
そんな思い込みを壊すのが、この訪問支援です。
生活の乱れは、心の乱れと直結しています。
朝起きられない、風呂に入らない、夜中までゲーム…。
これらの課題を、「環境の力」で整えるのが合宿と寮です。
▶ シュン君の例:
高校1年で引きこもり、生活は昼夜逆転。支援後、寮に入り3ヶ月で自然に朝起き、3食をとる生活に戻りました。現在は看護系の大学に進学しています。
「家では変われなかった子が、場所を変えただけで変わる」
これは決して珍しいことではありません。
「勉強が遅れてしまった」「もう無理かも」
そんなふうに感じていた子どもたちが、自分のペースで学び直せる環境。それが、私たちが提携する通信制高校・サポート校です。
▶ カズキ君の例:
家庭内暴力まで起きていたカズキ君は、転校後に学び直しを始め、現在は区役所で公務員として勤務しています。
「学びを取り戻す=自信を取り戻す」
学ぶことが楽しいと思える場所を、子どもたちに用意します。
ある程度生活リズムが整い、学ぶ姿勢も戻ってきたら、次のステップは「社会との接点」を持つこと。
いきなり就職ではなく、短時間のアルバイトやインターンで、“社会の空気”に少しずつ慣れていきます。
▶ サコウ君の例:
通信制高校での学び直し後、インターンを通じて企業との接点を増やし、プライム上場企業への内定を獲得しました。
「自分には無理だと思っていた」
そんな気持ちが、現実の体験によって変わっていくのです。
ここまで来たら、いよいよ「未来の設計」をしていきます。
公務員、大学進学、資格取得、海外留学など、それぞれの子どもに合わせた“自分らしいゴール”を一緒に見つけ、実現に向けて伴走します。
▶ Y子さんの例:
10年間引きこもっていたY子さんは、保育士の資格を取り、現在は公務員として地域で活躍しています。
「引きこもりの過去が、今の自分の強みになった」
これは、私たちが支援するすべての子どもたちに共通するメッセージです。
7つのステップは、単なる“支援プログラム”ではありません。
それは、一人ひとりの人生を支えるための“回復の地図”です。
支援は一歩一歩の積み重ねです。
でも、地図があれば、今どこにいて、どこを目指すのかが明確になります。
次章では、その7つのステップがどのような“実例”で実現されてきたのか、16人の成功事例から深掘りしていきます。
「本当に変われるの?」「うちの子だけは無理なんじゃ…」
そんな疑いと不安を抱えたまま、私たちのもとへ来られるご家庭は少なくありません。
でも、“変わった子どもたち”が確かにここにいるのです。
しかも、一人や二人ではありません。
ここでは、当協会の支援を経て、社会復帰を果たした16人のリアルなストーリーを、簡潔にご紹介します。
詳しくは こちら
【1】Y子さん|10年引きこもり→保育士→公務員
中学2年で不登校に。そのまま10年間、完全に引きこもり状態に。
24歳の時、「親知らずの痛み」が外に出るきっかけとなり、支援を開始。
アルバイト経験後、通信制高校・短大を経て保育士に。現在は公務員として子育て支援の現場で働いています。
【2】カイト君|中1不登校→家庭訪問→通信制高校→自衛隊
最初はエアガンで家族や支援員を撃つほどの拒否反応がありました。
しかし、訪問支援で徐々に信頼を築き、フリースクール通学から高校へ進学。
その後、自衛隊に入隊し、2024年には後輩の卒業式に参加するほど成長しました。
【3】カズキ君|中高一貫→成績不振→家庭内暴力→区役所勤務
名門中高一貫校に入学するも、学業についていけず不登校に。
支援開始時は暴言・暴力もありましたが、通信制高校へ転校し生活改善。
現在は区役所で公務員として地域福祉に貢献しています。
【4】リョウタ君|不登校→家庭訪問→通信制高校→航空自衛隊
親の呼びかけにも応じなかったリョウタ君。支援員の訪問を通じて外出を始め、通信制高校へ。
その後、航空自衛隊へ入隊し、厳しい訓練にも耐えながら自律を実現しました。
【5】タツマ君|中1引きこもり→フリースクール→難関大学→公務員
巣鴨中で不登校に。支援を経て通信制高校・予備校・難関私立大学へ進学。
現在は公務員として福祉分野で活躍しています。中学時代から約10年かけての逆転劇でした。
【6】佐藤渉太君|高校1年不登校→通信制高校→農業大学→JA内定
スポーツ推薦で進学するも人間関係がうまくいかず引きこもりに。
通信制高校で再スタートし、農業大学へ進学。JAに内定が決まり、地域貢献の道へ進んでいます。
【7】シュン君|高1引きこもり→寮生活→看護系大学へ進学
引きこもり状態で生活リズムは完全に崩壊。
生活改善合宿を経て寮に入り、自律的な生活へ。予備校で学び、看護系大学へ合格しました。
【8】W君|通信制高校→引きこもり→支援再開→自衛隊へ
高校入学後に再び引きこもり状態に。
支援再開後、自信を取り戻し、自衛隊での厳しい生活にも順応。いまでは後輩の相談役に。
【9】G君|高校中退→フリースクール→美大合格→後輩指導
美術に興味を持ちながらも高校中退。
8ヶ月の引きこもりを経て、支援によって再び筆をとり、美大に合格。現在は学生インターンとして後輩支援にも関わっています。
【10】ヨッシー君|中学不登校→海外留学挫折→青山学院大学→IT企業へ
不登校後、海外留学を試みるも環境になじめず帰国。
支援によって再出発し、青学進学→大手IT企業に就職というルートを切り拓きました。
【11】サコウ君|通信制高校→インターン→プライム上場企業就職
学校に適応できず通信制高校に転校。
支援によってインターンを重ね、プライム上場企業の内定を獲得しました。生活改善の力が大きかったと語ります。
【12】W君(発達障害)|通信制高校→看護系大学へ
発達特性と過去の入院歴があり、将来を悲観していたW君。
支援を通じて特性を活かす方向を探り、看護系大学に進学。いまは「過去の経験を看護に活かしたい」と語っています。
【13】N君|中3不登校→2年引きこもり→カナダ留学→農業大学進学
完全に引きこもっていたN君。支援で少しずつ外出し始め、やがて海外留学を経験。
現在は農業大学に進学し、地方での就農も視野に入れています。
【14】S君|中2暴力→包丁事件→アウトリーチ支援→大学進学準備中
家庭内暴力が激しく、支援員が包丁で威嚇されたことも。
しかしeスポーツやピアサポートを通じて変化し、現在は通信制高校で学びながら大学受験に向け猛勉強中。
【15】K君|高1完全引きこもり→寮生活→講演会登壇
一歩も外に出られなかったK君も、支援によって学生寮での生活へ移行。
その後、通信制高校に通いながら、不登校講演会で自身の体験を発表するまでに成長しました。
【16】エイタ君|中2完全不登校→通信制高校→カナダ留学→大学進学
中2で完全に不登校状態に。支援開始後、フリースクール→カナダ留学へ。
高校卒業後は工学院大学に進学し、学びを続けています。
以上が、私たちがこれまで支えてきた“16人のリアルストーリー”です。
どの子も、最初は「無理だ」「うちの子に限って…」と言われていました。
でも、“伴走型の支援”を受けて、自分の人生を取り戻したのです。
「やり直せる力」は、どの子にも眠っています。
必要なのは、“信じて伴走してくれる大人”がそばにいること。
次章では、「なぜ支援は早い方がいいのか」「引きこもりステージ3以降に潜むリスク」について詳しく解説します。
「もう少し様子を見ましょう」
「本人がその気になるまで待った方がいいのでは…」
そう思って時間を置いた結果、状況が悪化してしまった――
これは、実際に多くのご家庭で起きていることです。
支援のタイミングが遅れると、子どもは「不登校」から「引きこもり」へ、そして「社会との断絶」へと進んでしまいます。
特に、「引きこもりステージ3」以降では、ご本人の生活や心の状態に深刻な影響が出はじめ、ご家庭だけの力での回復が難しくなる段階です。
当協会では、不登校・引きこもりを5段階に分類しています。
ステージ3に入ると、以下のような状態が見られます:
ここで対応を誤ると、ステージ4(暴力や破壊的行動)、ステージ5(心身の機能低下・完全な引きこもり)に進んでしまいます。
中学から不登校が始まり、何となく時間だけが過ぎてしまった…。
その結果、18歳、20歳と年齢だけが進み、「今さら…」という気持ちが本人にも親にも芽生えてしまいます。
▶ Y子さんのケース
中学2年から10年間の引きこもりを経て、24歳で支援開始。
外に出るきっかけは「親知らずの痛み」でした。
そこからアルバイト・通信制高校・短大と進み、最終的には保育士・公務員として社会復帰しました。
手遅れではありませんが、年齢が上がるほど再出発にかかる時間とエネルギーは大きくなるのです。
「どうせ自分はダメだ」
「外に出たら迷惑をかける」
ステージ3以降になると、子どもは自分自身を強く否定するようになります。
玄関のチャイムに怯えたり、来客に過剰反応したり、「知らない人」と接することに強い不安を感じます。
▶ リョウタ君の例
最初は家庭訪問も拒否。
しかし支援員の定期的な訪問と、母親へのコーチングを通じて徐々に心を開き、通信制高校入学→航空自衛隊入隊へと進みました。
「関わるのが怖い」という壁は、第三者との“適切な距離感”の関わりで乗り越えることができます。
ステージ4に進むと、感情をうまくコントロールできず、親に対する暴言・暴力、物を壊す行動が現れることもあります。
ゲーム機やスマホへの過度な依存から、制限しようとすると怒り出し、暴れる…そんな家庭も少なくありません。
▶ S君の事例
中2で包丁を持ち出し、支援員を威嚇。
しかしeスポーツやピアサポートなどで「好き」を活かした関わりを続け、現在は通信制高校に在籍し、大学進学を目指すまでに回復。
暴力の裏にあるのは、助けてほしいという心の叫びです。K君の詳細はこちら
「この子の将来はどうなるんだろう」
「何もできない自分が情けない」
子どもの状態が悪化すると、支援をしたいと思っていた親御さんの心も、少しずつ疲弊していきます。
▶ 私たちがまず支えるのは、「親の心」です。
月1回のZoomコーチングやメール相談を通じて、
「話すだけでも心が軽くなった」
「こんなに丁寧に聞いてくれたのは初めてだった」
という声がたくさん届いています。
支援の出発点は、「親が一人で抱え込まないこと」なのです。
「様子を見ましょう」という言葉には注意が必要です。
それが“放置”になってしまえば、子どもは“自分に関心がない”と受け取ることさえあるのです。
見守るべきときもありますが、それは“適切な支援のタイミング”を逃さない”ための見守りでなければなりません。
年齢が上がるほど、社会復帰の難しさは増します。
家庭内での緊張感が長く続けば、家族関係も壊れてしまう恐れがあります。
だからこそ――今が「回復のチャンス」なのです。
子どもが完全に拒否していても、親が動くことで状況は変わります。
まずは支援の全体像を知ることから、私たちと一緒に始めてみませんか?
「支援団体って、どこも同じじゃないの?」
「近所のスクールカウンセラーやフリースクールに任せていれば…」
そんなお声をよく耳にします。
確かに、全国には多くの不登校・引きこもり支援団体があります。
しかし、当協会の支援は“他とはまったく異なる3つの大きな特徴”を持っています。
多くの支援団体は、拠点周辺の通所型やオンライン支援が中心です。
しかし、子どもが外に出られない状態(ステージ3以上)では、本人から支援にアクセスするのは極めて困難です。
私たちは、東京を中心に活動しながらも、北海道から沖縄まで、全国どこでも支援員がご家庭を訪問し、必要に応じて連携先とも協力しながら支援を行います。
▶ ヨッシー君(山梨県在住)も、家庭訪問をきっかけに外へ出るようになりました。
不登校からの再出発を支援され、最終的には青山学院大学に進学し、現在は大手IT企業で社会人として活躍しています。
「とりあえず学校に戻す」――これがゴールになっている支援も多く見受けられます。
けれども、学校に戻ったとしても、社会に出る準備ができていなければ、再び引きこもるリスクが高いのが現実です。
当協会では、不登校・引きこもりの状態から、学び直し・職業体験・進学・就職・自律までを一貫して支援。
公務員や自衛隊、看護師、IT企業などへの進路を実現した支援例は多数あります。
▶ Y子さん(10年引きこもり)やサコウ君(通信制高校→プライム上場企業)などがその証です。
「その先」まで一緒に見据えてくれる支援が、安心につながります。
家庭の状況、子どもの性格、支援のステージ――
どれ一つとして同じものはありません。
だからこそ、私たちはテンプレート通りの支援ではなく、毎家庭に合わせた「オーダーメイド型支援計画」を立てて進めていきます。
その都度、保護者の方とのメール相談やZoom面談を通じて、進捗を確認しながら軌道修正も行います。
この柔軟性が、長期的な信頼関係と変化を生むのです。
▶ たとえば、寮生活を嫌がったK君には「家庭訪問+在宅支援+対面学習」の3本立て支援を実施。
最終的には通信制高校に転校し、講演会で自身の体験を語るまでに成長しました。
私たちが目指しているのは、「○○すれば変わる」という一律の支援ではありません。
大切なのは、「この子がどうしたら前に進めるか」を常に一緒に考え続けることです。
そのために、訪問支援員も、学生インターンも、保護者コーチも、「人と人との関係性」を大事にしながら関わります。
それが当協会が40年以上続けてきた「伴走型支援」の本質です。
支援は、制度でもプログラムでもなく、「人の力」です。
そんなご家庭が、私たちの支援を受けて、変化の兆しを見せています。
大切なのは、今のあなたの状況に寄り添い、無理なく前進できる方法を一緒に探すこと。
全国どこでも、あなたのご家庭に合わせた支援が可能です。
「何から始めればいいのか分からない」
「本人が動かないのに、親だけ動いても意味がないのでは…」
多くの保護者がそう感じながら、時間だけが過ぎていく――
これこそが、最も避けたい状況です。
ですが、安心してください。
お子さんが動き出していなくても、保護者ができる行動はたくさんあります。
そして、その一つひとつが、確実に“回復への布石”になります。
「うちの子はどの段階にいるのか?」
それが分かるだけで、支援の方向性がハッキリしてきます。
▶ 当協会では、5段階のステージ判定表を活用し、不登校・引きこもりの状態を“見える化”しています。
「まだそこまで深刻じゃないと思っていたけど、すでにステージ3だった…」
という声は、実際によく聞かれます。
まずは親御さんご自身が、“正確な現状認識”を持つこと。それが支援の出発点です。
「相談」と聞くと、「本人が来ないと意味がない」と感じるかもしれません。
しかし、本人が動かない今こそ、保護者からの相談が最も重要なのです。
▶ 当協会では、メールによる個別相談を受け付けています。
「まずは聞いてもらえるだけで、気持ちが軽くなった」
そんな声もたくさん届いています。
お子さんの心に届く言葉を選ぶには、「知識」と「練習」が必要です。
▶ Zoomでの親向けコーチングでは、
たとえ一言のかけ方が変わるだけでも、家庭内の空気がガラッと変わることがあります。
子どもが一歩踏み出すためには、「責められない空気」「肯定される雰囲気」が欠かせません。
そのために、親自身の気持ちを整えることも大切です。
▶ 実践例:
子どもが安心できる家庭環境を整えること=回復の土台を作ることなのです。
もし今、「何もできない」と感じているなら――
私の書籍を手に取ることも、最初の一歩です。
これらの本には、実際に支援した子どもたちの事例や、保護者の声、回復のステップがわかりやすくまとめられています。
“知ること”が、親の心を強くし、支援の判断力を高めてくれます。
迷っているなら、まずはメールでご相談ください。
状況を変えるために、遅すぎるということはありません。
不登校や引きこもり――
子どものことを想うあまり、保護者の方はいつも「自分が何か間違えたのでは」と自分を責めがちです。
でも、どうか思い出してください。
「子どもを変えよう」とするのではなく、「子どもと一緒に変わっていく」――
それが、再出発のための本当のスタートラインです。
第4章でご紹介した16人の事例は、すべて実際に私たちが支援した子どもたちです。
10年の引きこもりを経て公務員になったY子さん。
暴力的だった中学生が、今は大学受験を目指すS君。
「もう手遅れだ」と思われていた子どもたちも、確かな支援の中で、自分の道を見つけていきました。
私たちは、7つのステップを通じて支援を行っています。
この流れを、一人ひとりに合わせてオーダーメイドで設計します。
机上の空論ではなく、現場の実践を重ねた“本物の支援”です。
子どもが動けないなら、まずは親が一歩踏み出すこと。
それが、家庭の空気を変え、子どもの心にも変化のきっかけを与えます。
Zoomでの親コーチング、メール相談、書籍を読むこと――
そのどれもが、変化を生み出す「最初の一歩」になります。
▶ 実際に支援を受けたあるお母さまは、こう語っています。
「メール一本で、本当に変わるのかと半信半疑でした。でも、子どもが少しずつ表情を取り戻し、今では朝自分で起きるようになりました。」
子どもたちには、本来持っている“生きる力”があります。
その力が、今は眠っているだけ。
その芽を再び伸ばすには、家庭という安心の土壌と、ともに歩む支援の存在が必要です。
私たちは、その支援を40年以上、1万人以上の子どもたちとご家庭に提供してきました。
成功率は9割以上――これは、特別な才能ではなく、“あきらめなかった親”と“寄り添った支援者”がいたからこそ実現した数字です。
「うちの子にも、まだ可能性はありますか?」
そう聞かれたら、私はいつもこう答えます。
「もちろんです。むしろ今が、変わる最大のチャンスです」
どんなに長く引きこもっていても、何もしゃべらなくても、暴れていても――
一人ひとりに合った道筋があります。
そして、あなたのお子さんにも、社会に必要とされる未来が必ずあるのです。
▶ 今できること
次の章では、支援マップやステージ判定表のご案内、そして無料相談の受付方法をご紹介します。
ここまで読み進めてくださったあなたへ――
「うちの子も変われるかもしれない」
そんな希望の芽が、少しでも心に芽生えたのなら、それが再スタートの合図です。
不登校や引きこもりは、決して珍しい問題ではありません。
でも、「どこに相談すればいいのか」「何を基準に動けばいいのか」――
そこが見えないまま、迷い続けているご家庭はとても多いのです。
私たちは、そんな保護者の方のために「見える支援」を整えています。
お子さんの状態を客観的に捉えるために、当協会では5段階のステージ判定表をご用意しています。
こうした観点から、「今、どの段階にいるのか?」を確認するだけでも、支援の方向性が見えてきます。
このステージ判定表は、無料相談フォームにお申し込みいただくことでご案内しております。
支援の必要性を判断する目安として、ぜひご活用ください。
当協会が40年以上の支援活動のなかで体系化した「支援マップ」は、
不登校から引きこもり、そして就職・自律に至るまでの“再スタートの道のり”を7ステップで見える化したものです。
それぞれのステップが、お子さんとご家庭に寄り添って進められる“伴走型支援”として設計されています。
「今、どこにいて、どこを目指すのかがわかっただけで、不安が消えました」
という声も、多くのご家庭から届いています。
不安を抱えている方にこそ、まずは一歩を踏み出してほしいと願っています。
「今のうちの子に支援は必要なのか?」
「何を優先すべきなのか?」
そんなお悩みを、どうぞ気軽にご相談ください。
💻 Zoom面談(初回30分無料)
▶ お申し込みフォーム:https://yoboukyoukai.com/soudan/
◆ 迷っているなら、今が“動くとき”です
お子さんの未来は、まだ閉ざされていません。
そして、今この瞬間が、「変化の入口」になるかもしれません。
必要なのは、完璧な準備ではなく、“相談してみよう”という親の一歩です。
私たちは、その一歩に全力で寄り添い、伴走します。
未来を変える支援は、ここから始まります。